- 喘息とは
- 喘息の症状をチェック
- 喘息を発症する原因と2つのタイプ
- 大人の喘息と子どもの喘息に違いはある?
- 喘息の方がやってはいけないこと
- 喘息の診断と検査
- 喘息の治療方法
- 喘息を治療しないまま放っておくとどうなる?
喘息とは
 喘息は、慢性的な炎症によって気道が狭くなる病気です。気道が敏感になっているため、普段は無症状でも、冷気、煙、ストレスなどのちょっとした刺激によって呼吸困難・咳・痰、喘鳴といった症状が引き起こされます。
喘息は、慢性的な炎症によって気道が狭くなる病気です。気道が敏感になっているため、普段は無症状でも、冷気、煙、ストレスなどのちょっとした刺激によって呼吸困難・咳・痰、喘鳴といった症状が引き起こされます。
喘息の症状をチェック
喘息には、主に以下のような症状があります。小さな子どもの場合、泣いてしまったり、不機嫌になったりすることもあります。

- 呼吸のしづらさ、呼吸困難
- 咳
- 痰
- 喘鳴(ゼイゼイ、ヒューヒューという異常な呼吸音)
- 息を吸う時、肋骨が浮く
- 顔色が悪い
喘息を発症する原因と
2つのタイプ
喘息は、アトピー型と非アトピー型に分けられ、それぞれ原因が異なります。
アトピー型
ハウスダストなどのアレルゲンが原因となって起こる喘息です。
子どもが発症する小児喘息は、アトピー型が多くなります。
非アトピー型
タバコなどの煙、気温・気圧の変化、ストレスなどが原因となります。
大人になってから発症する成人発症型喘息は、非アトピー型が多くなります。
大人の喘息と子どもの喘息に違いはある?
大人の喘息の場合
 大人の喘息は、小児喘息から以降するタイプと、成人になって初めて発症するタイプ(成人発症喘息)に分けられます。
大人の喘息は、小児喘息から以降するタイプと、成人になって初めて発症するタイプ(成人発症喘息)に分けられます。
成人発症喘息は、40~60代の中高年での発症が目立ちます。また、先述の通り非アトピー型が多くなります。
子どもの喘息の場合
 ほとんどが2~6歳くらいで発症します。そのうち、約70%が思春期から青年期に自然に軽快しますが、小児期にきちんと治療を行うことで、成人喘息へと以降するリスクを下げることができます。
ほとんどが2~6歳くらいで発症します。そのうち、約70%が思春期から青年期に自然に軽快しますが、小児期にきちんと治療を行うことで、成人喘息へと以降するリスクを下げることができます。
大人の喘息と症状に大きな違いはありませんが、特に小さな子どもの場合、言葉でうまく症状を伝えられないため、親御さんの「気づき」が大切になります。泣いたり不機嫌な状態が続いているが原因が分からないという場合には、当院にご相談ください。
幼稚園や学校では、掃除の時にマスクをつける、運動時にはしっかりと準備体操を行うなど、発作を予防するための対策が必要となるため、事前に相談しておきましょう。
小児喘息の多くは、アトピー型の喘息です。
喘息の方が
やってはいけないこと
ハウスダストを吸う
ダニ、埃、ペットの毛などのハウスダストを吸ってしまうと、症状が悪化します。
小まめな掃除や洗濯、換気などにより、ご自宅のハウスダストをできる限り減らしましょう。
原因・刺激となる食べ物
発作を誘引する食べ物が分かっている場合には、その食べ物を食べないようにしてください。
また、唐辛子などの刺激の強いものも、気道を刺激するため、避けましょう。
強炭酸・冷たい飲み物
強い炭酸、冷たい飲み物は、気道を刺激します。できれば、避けた方が良いでしょう。
激しい運動
息が切れるような激しい運動は、発作の原因となることがあります。ウォーキング程度の軽い運動であれば通常は問題ありません。
アスピリン・コデインの
内服
いずれも、症状を悪化させるおそれがあります。市販薬にも含まれているため、購入時には十分に注意をしてください。
喘息の診断と検査
診断の目安
喘息は、以下のようなポイントについて調べた上で、総合的に診断します。
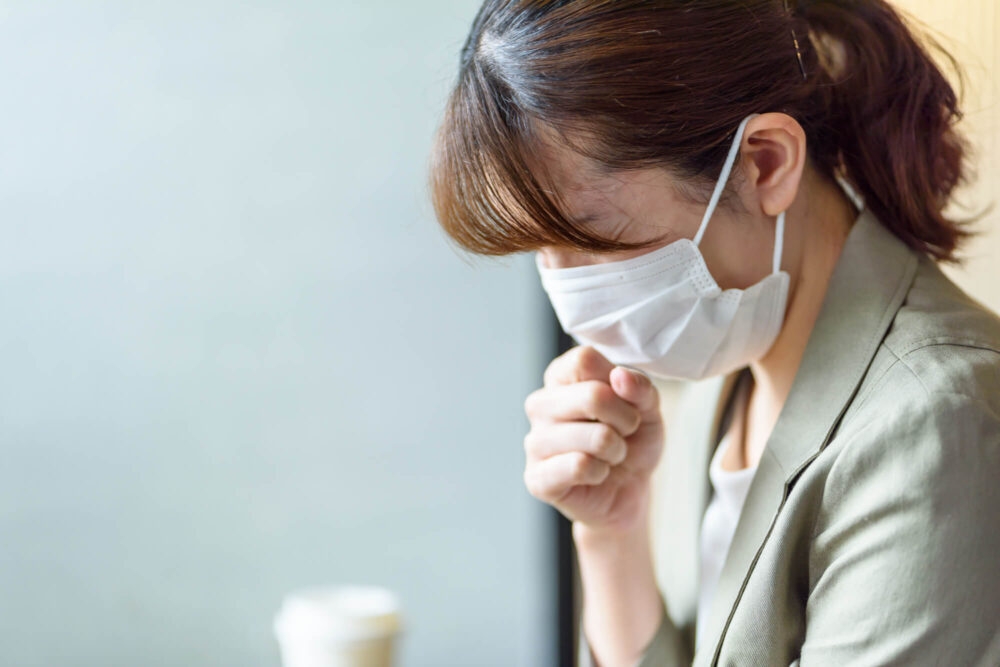
- 発作性の呼吸困難・咳・苦しさ・喘鳴を繰り返し、特に夜間・早朝に強くなる
- 気管支の狭窄の程度が大きく変化する
- 気管支が刺激に対して過敏に反応する
- アレルゲンに反応している様子が認められる
- 気道炎症が認められる
- 認められる症状が喘息以外の病気によるものではない
問診で尋ねること
喘息の診断では、問診で得られる情報がとても重要になります。
問診では、主に以下のようなことについてお尋ねします。

- 症状の種類、程度
- 症状が出た時期
- 症状の頻度
- 症状が出る・強くなるタイミングや時間帯
- アレルギーの有無、既往歴、家族歴
- 生活環境(喫煙・飲酒・ペットの有無など)
喘息の際に行う検査
呼吸機能検査
ピークフローメーターという装置を用いて、呼吸器の機能を調べます。肺活量、吐き始め~吐き終わりまでの時間、吐く速さを測定します。
喘息が疑われる症例において、もっとも基本となる検査です。
血液検査
アレルギーが疑われる場合には、アレルゲンを特定する血液検査を行います。
気道過敏性試験
発作を誘発する薬を用いて、気道の過敏性について調べます。発作が出る薬の濃度を調べ、判定します。
皮膚テスト
アレルギーが疑われる場合に行う検査です。疑わしいアレルギンのエキスを皮膚に接触させ、その皮膚の反応を観察することで判定します。
胸部レントゲン検査
他の呼吸器疾患との鑑別、肺炎の合併の有無などを調べるために行います。
その他
心電図検査、心臓超音波検査、胸部CT検査、気管支鏡検査などを行うこともあります。
喘息の治療方法
喘息の治療は、薬物療法が中心となります。
ハウスダストなどが原因となっている場合には、ハウスダスト対策のための指導・アドバイスもいたします。
薬物療法
薬物療法では、発作を予防する長期管理薬、発作が起きた時に使用する発作治療薬を処方します。
発作を予防する
「長期管理薬」
気道の炎症を抑える薬、気道を広げる薬を使用します。継続して使用することで、しっかりとした効果が得られます。発作が起こらないからといって、自己判断で治療をやめないようにしましょう。
発作が起きた時に使用する「発作治療薬」
気管支を速やかに広げ、呼吸をしやすくする薬です。
内視鏡療法
薬物療法で十分な効果が得られない場合には、気管支サーモプラスティ(BT)という内視鏡治療を行うことがあります。
この治療が必要になった場合には、提携する病院へとご紹介いたします。
喘息を治療しないまま
放っておくとどうなる?
 どのような病気にも言えることですが、喘息も放置してよい病気ではありません。
どのような病気にも言えることですが、喘息も放置してよい病気ではありません。
喘息を放置した場合には、気道のリモデリングが起こる可能性が高くなります。
「喘息かもしれない」と感じた時には、お早目に当院にご相談ください。
喘息の難治化に繋がる
「気道のリモデリング」
喘息を放置していると、慢性的な炎症によって気道の壁が厚く・硬くなる「リモデリング」が進みます。リモデリングが進むほど、喘息は難治化し、治療を行っても症状がなかなか良くなりません。また、発作も起こりやすくなります。




