頸椎の構造
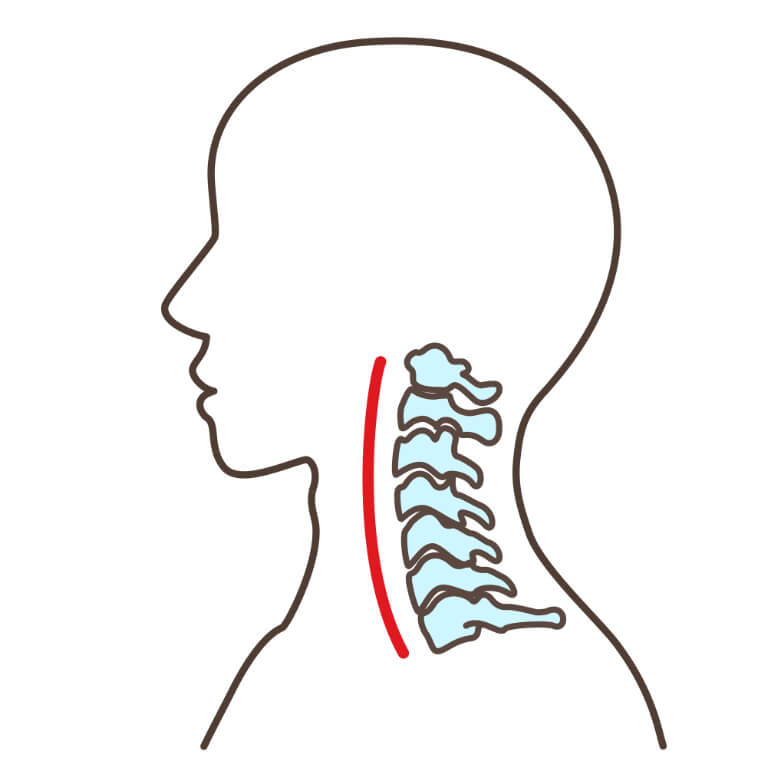 頸椎とは、いわゆる“首の骨”のことを指します。もう少し詳しく見ると、頸椎は7つの椎骨、そしてその間にある椎間板で構成されていることが分かります。そして頸椎の後方には、脳から伸びる重要な神経「脊髄」と、その通り道である「脊柱管」が存在します。
頸椎とは、いわゆる“首の骨”のことを指します。もう少し詳しく見ると、頸椎は7つの椎骨、そしてその間にある椎間板で構成されていることが分かります。そして頸椎の後方には、脳から伸びる重要な神経「脊髄」と、その通り道である「脊柱管」が存在します。
頸椎は、約5kgもある頭部を支えています。重さを分散させるため、横から見ると中央部がやや前方に出る形で弓なりになっています。
頸椎症とは
頸椎症とは、加齢に伴う椎間板の変性、骨の棘(骨棘)の形成、靭帯の肥厚などによって、神経が圧迫される病気です。
圧迫される神経によって、大きく以下のように分類されます。
頸椎症性脊髄症
脊柱管を通る「脊髄」が圧迫されて起こる頸椎症です。
痛みなどの症状が、多くは左右両側に現れます。
頸椎症性神経根症
脊髄から左右へと分岐する「神経根」が圧迫されて起こる頸椎症です。
痛みなどの症状が、主に左右どちらかの片側に現れます。
初期症状はある?
頸椎症の主な症状
初期症状として下記が挙げられます。
初期症状
- 首や肩の痛み
- 肩甲骨の痛み
- 肩こり
主な症状
- 手、腕の痛みやしびれ
- 握力低下
- 手先の細かい作業の困難
- 脚のしびれ
- 足裏の違和感
- 歩行障害
- 排尿障害、排便障害
頸椎症の原因
 加齢に伴う椎間板の変性を主な原因として発症します。変性が進むと骨棘が形成され、靭帯も厚みを増します。こういった老化によって、脊髄や神経根が圧迫されるのです。その他、不良姿勢、首・肩の筋力低下なども、頸椎症の発症へと影響します。
加齢に伴う椎間板の変性を主な原因として発症します。変性が進むと骨棘が形成され、靭帯も厚みを増します。こういった老化によって、脊髄や神経根が圧迫されるのです。その他、不良姿勢、首・肩の筋力低下なども、頸椎症の発症へと影響します。
また日本人は欧米人と比べて脊柱管の幅が狭く、このために脊髄の圧迫も起こりやすいものと考えられます。
頸椎症の検査方法
頸椎症が疑われる場合には、主に以下のような検査を行います。
なお身体所見では、首を後方へ反らした時に痛みが強くなるかどうかを確認します(スパーリングテスト)。
レントゲン検査
頸椎の変性の有無について調べます。ただ、中年以降の方にはほとんど場合、変性が認められます。身体所見、MRI検査とあわせて診断することが大切です。
MRI検査
脊髄、神経根への圧迫の有無や程度を調べます。
頸椎症の治療方法
まずは保存療法を行い、十分な効果を得られない場合に手術を検討します。
保存療法
安静、痛み止めの内服、ブロック注射、カラーの装着などを行います。
痛みが落ち着いてからは、リハビリテーションも有効です。
手術療法
前方除圧固定術、椎弓形成術、後方除圧固定術などの中から、病態に合わせた術式が選択されます。
手術が必要になった場合には、すぐに高次医療機関へとご紹介いたします。
頸椎症に対する
リハビリテーション
 姿勢訓練、肩関節まわりのストレッチ、マッサージ、筋力トレーニングなどを行います。これにより、可動域の回復、頸椎への負担軽減が期待できます。
姿勢訓練、肩関節まわりのストレッチ、マッサージ、筋力トレーニングなどを行います。これにより、可動域の回復、頸椎への負担軽減が期待できます。
手指の動きが低下している場合には、細かな動作機能を回復させる訓練も行います。
頸椎症を予防するには
頸椎症の予防のためには、以下のような対策が有効です。
姿勢の改善
背筋を伸ばし、首から腰にかけて、横から見た時の自然な曲線を維持できるよう努めましょう。
特にデスクワークをする時、手元の細かな作業をする時は、姿勢が悪くなりがちです。
適度な運動
適度な運動で全身の柔軟性と筋力の維持・向上を目指しましょう。
特に、首・肩を使うストレッチ・筋力トレーニングがおすすめです。
環境を整える
机や椅子、ベッド、枕など、姿勢などに影響する身の回りの環境を整えましょう。立っている時、座っている時、寝ている時のいずれの場合も、首に負担のかからない自然な姿勢でいることが大切です。




