- 片脚立ちで靴下がはけない・家の中で躓いたり滑ったりする
- 他にもこんな症状はありませんか?
- なぜロコモティブシンドロームになるの?主な原因とは
- ロコモティブシンドロームの予防方法
- ロコモティブシンドロームの治療方法(ロコトレ)
- 当院の運動リハビリテーションをご利用ください
片脚立ちで靴下がはけない・家の中で躓いたり滑ったりする
それはロコモティブシンドロームかも…
 ロコモティブシンドローム(運動器症候群)とは、運動器の衰えを原因として、歩く等の移動機能が低下し、要介護状態、または近い将来に介護が必要になる可能性の高い状態を指します。
ロコモティブシンドローム(運動器症候群)とは、運動器の衰えを原因として、歩く等の移動機能が低下し、要介護状態、または近い将来に介護が必要になる可能性の高い状態を指します。
移動機能とは具体的に、立ち座り・歩行・階段の上り下りのことを意味しますが、片足立ちで靴下がはけない・家の中で躓いたり滑ったりするといった場合にも、ロコモティブシンドロームが疑われます。
ロコモティブシンドロームは、メタボリックシンドローム、認知症とともに、健康寿命の短縮や寝たきりの原因となりやすい因子です。早期に医療が介入することで、ロコモティブシンドロームの進行を食い止めたり、遅らせたりすることが可能ですので、気になる方はぜひ一度当院にご相談ください。
他にもこんな症状はありませんか?
以下のような症状がある場合には、ロコモティブシンドロームが疑われます

- 立ち座りの際に必ず手をつく、手すりを持つ
- 信号が青のうちに横断歩道を渡り切れない
- 15分以上続けて歩くことができない(休み休み歩く)
- 階段の上り下りが辛い、手すりがないと難しい
- 小さな段差に躓く、段差のないところで躓く
- 買い物などで、2kg程度の荷物を持って帰宅することが難しい
- 料理や洗濯、掃除などの家事でできないことが増えてきた
なぜロコモティブシンドロームになるの?主な原因とは
ロコモティブシンドロームの原因は、運動器の衰えです。そして運動器の衰えは、運動器の疾患、運動器の機能不全によって進行します。
運動器の疾患
変形性膝関節症・変形性脊椎症・脊柱管狭窄症・関節リウマチなどに伴う痛みや痺れ、可動域の減少、筋力低下、骨粗しょう症による骨折などを原因として、筋力や柔軟性、バランス能力などが低下します。
運動器の機能不全
加齢、運動不足、閉じこもり、病気療養などによる筋力や柔軟性、バランス能力の低下、反応の遅れ、運動速度の低下などが運動器の機能不全に該当します。
ロコモティブシンドロームの予防方法
ロコモティブシンドロームの予防のためには、まず大前提としてロコモティブシンドロームの危険性を把握する必要があります。対策をせずにいると移動機能が低下し、肉体的な衰え、社会的活動の減少、さらには意欲の低下などに繋がり、その先には要介護状態、寝たきりなどがあることを理解することが大切です。
その上で、具体的な予防として、タンパク質をはじめとする十分な栄養の摂取、適度かつ継続的な運動を行います。また肥満の方は、食事・運動に気をつけて適正体重までの減量を図りましょう。
若いうちからの運動習慣が大事です
 ロコモティブシンドロームの多くは、60代や70代で見つかります。そのため予防という意味では、40代や50代から取り組みが重要となります。40代や50代というのは、体の衰えを自覚しやすい時期でもあります。そういった時に「もう歳だから仕方ない」と考えるのか、「予防のために体を鍛えよう」と思うのかが、大きな分かれ道となります。
ロコモティブシンドロームの多くは、60代や70代で見つかります。そのため予防という意味では、40代や50代から取り組みが重要となります。40代や50代というのは、体の衰えを自覚しやすい時期でもあります。そういった時に「もう歳だから仕方ない」と考えるのか、「予防のために体を鍛えよう」と思うのかが、大きな分かれ道となります。
とはいっても、スポーツジムで重いダンベルを持ち上げたり、倒れるくらい走り込んだりする必要はありません。リハビリ施設や自宅でできる簡単な筋力トレーニング、散歩や買い物を兼ねたウォーキングなどでも、ロコモティブシンドロームを予防する運動は可能です。
こういった運動習慣が20代や30代から開始できれば理想的ですが、大切なのは「気づいた時に始められるか」ということです。「歳だから」「今さら…」とは考えず、ぜひ一度、当院にご相談ください。
ロコモティブシンドロームの治療方法(ロコトレ)
ロコモティブシンドロームの治療では、足腰の筋力アップ、バランス能力の改善を目指します。
運動機能がどの程度あるかによって強度も変わってきます。ここでは、もっとも基本的なトレーニング(ロコトレ)である片脚立ちとスクワットをご紹介します。
※室内で行う場合、靴下だけ履いた状態、スリッパを履いた状態だと滑りやすく、転倒の原因となります。裸足、または室内用シューズを履いた状態で行ってください。
片脚立ち
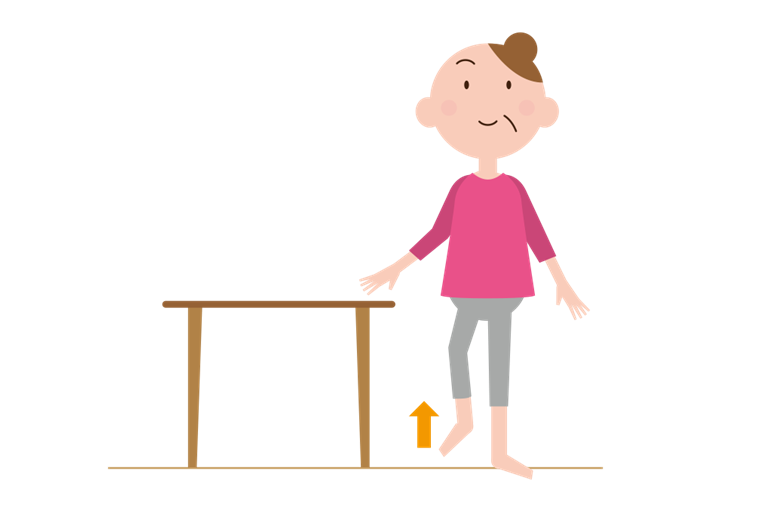
- 壁や柱、重く動かない家具などの近くに立ちます。
- 右手を、壁や柱、家具などにつきます。
- 右足を少し浮かせ、その状態を1分保ちます。高く上げる必要はありません。
- 今度は左手をつき、左足を同様に1分間、少し浮かせます。
- 両足それぞれ、1日3セットを行います。
スクワット
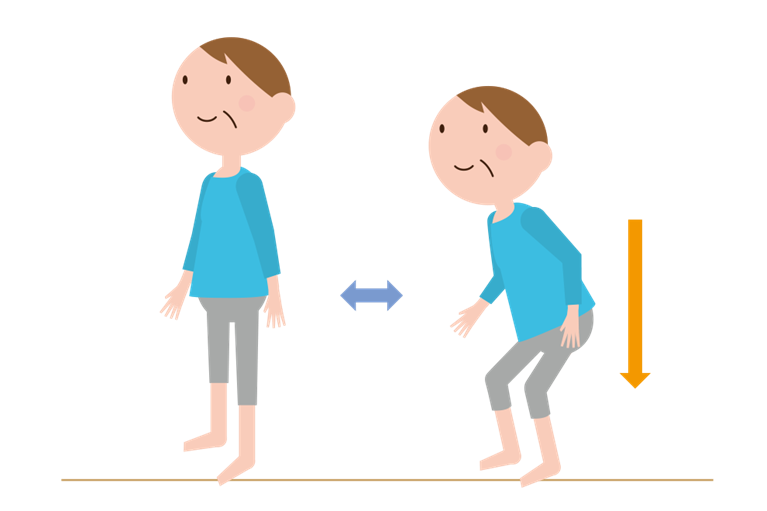
- 立った状態で、肩幅より少し広めに両脚を開きます。つま先は、約30°開きます。
- 膝が前方に突き出さないように、お尻を下げます。
- 膝を伸ばし、もとの立った状態に戻ります。
- 5回を1セットとし、1日3セット行います。
※お尻を落とせない・上げられない・転びそうになる方は、しっかりとした椅子やソファから立ち座りを繰り返すことで、スクワット運動ができます。
当院の運動リハビリテーションをご利用ください
上記の片脚立ち、スクワットは治療のほんの1例です。
当院では、お体や運動器の状態などに合わせたリハビリテーションを行っておりますので、ロコモティブシンドロームかもしれないと感じる方はぜひ一度ご相談ください。
医師の指導のもと、理学療法士が患者さん1人ひとりに合ったリハビリテーションを行って参ります。




